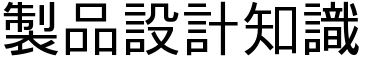設計品質向上のための仕組みをつくる
再発防止と未然防止の進め方
日時 2018年8月24日(金) 10:00~17:00
会場 日刊工業新聞社東京本社セミナールーム
主催 日刊工業新聞社
本セミナーは多くの皆様に受講頂き、好評のうちに終了しました。
<受講者様の声(抜粋)>
・実際の事例が取り入れられ、解説も親切で分かりやすかった。
・チェックリストの作り方でいつも悩んでいたが、今回の内容がヒントになった。
・設計者のエラーを防ぐ対策が重要だということが分かった。
・今後の業務に活用できる。
日刊工業新聞社様主催のセミナーに登壇します。
申し込み(日刊工業新聞社様ホームページ)
<概要>
製品の不具合は通販サイトの口コミやSNSで瞬く間に拡散していきます。公的機関による製品事故やリコールの情報公開も進みました。設計・開発部門の皆様は、設計品質に関してこれまでにないぐらいのプレッシャーを感じているのではないでしょうか。設計品質を向上させるために、様々な設計手法を試している企業も多いでしょう。設計手法はうまく使えば非常に高い効果を発揮しますが、実際に使い始めると、なかなかうまくいかないことが多いものです。なぜなら、設計手法は設計プロセスの一部に過ぎず、それだけで設計品質を向上させることは難しいからです。設計品質を向上させるためには、そのベースとなる考え方を理解することが重要です。その考え方の基本となるのが再発防止と未然防止への取り組みです。
本セミナーでは、実際に設計品質向上のための仕組みづくりに奔走してきた講師が、再発防止と未然防止の考え方について分かりやすく解説します。
セミナープログラム
❶設計品質を向上させるための考え方
1-1 設計に起因するトラブル事例
1-2 再発防止と未然防止の関係
1-3 なぜ未然防止が必要なのか
1-3-1 「時間がなくてできない」からの脱却
1-3-2 製品の不具合は隠せない時代
1-4 設計品質を向上させるための3つのポイント
1-4-1 人材(設計者/チェッカー/レビュア/承認者/仕組み構築者)
1-4-2 設計資産
1-4-3 設計プロセス
1-5 各フェーズで用いられる設計手法
1-6 設計の仕組みはMECE(ミーシー)で構築する
❷再発防止
2-1 再発防止の考え方
2-2 失敗(設計トラブル)のとらえ方
2-3 直接原因の究明と対策
2-4 根本原因の究明と対策
2-5 設計ルール作成のポイント
2-6 使えるチェックリストと使えないチェックリスト
2-7 設計者のエラーをいかに防ぐか
❸未然防止
3-1 未然防止の考え方
3-2 設計資産×人材×設計レビューで問題を発見する
3-3 設計レビューの進め方
3-4 リスクアセスメント
3-4-1 リスクの考え方
3-4-2 優先順位と妥当性の判断
3-5 未然防止手法の代表格:FMEA/FTA
3-6 未然防止の仕組みを設計プロセスに組み込む
❹ 活動の効果をさらに高める取り組み
4-1 リスクを低減させるためのポイント
4-1-1 ストレス・ストレングスモデル
4-1-2 製品の使われ方の明確化
4-1-3 ものは壊れる(フェールセーフ)
4-1-4 人は間違える(フールプルーフ)
4-1-5 3ステップメソッド(本質的安全設計の優先)
4-1-6 ハインリッヒの法則(ヒヤリハット)
4-2 設計者の品質に関する感度を上げる方法
4-3 設計効率向上のための取り組み
4-4 設計資産の蓄積に対する意識変革
4-5 近い将来の設計トラブル防止対策(設計資産が設計力を左右する)